1957年生まれ。1987年北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。1999年博士号取得(教育学)。1987~1989年稚内北星学園短期大学講師。1989~1991年同助教授。1991~2000年室蘭工業大学助教授。2000~2003年弘前大学助教授。2003~2016年9月同教授。2011~2014年同教育学部附属特別支援学校長。2014~2016年9月同教育学部附属特別支援教育センター長。2016年10月~教育心理支援教室・研究所『ガジュマルつがる』代表。
肩書きや社会的立場ではなく、その人自身と向き合う
好奇心と冒険心。松本さんの研究の根底にあるのは、「目の前に転がっている不思議に飛び込まずにはいられない!」というような、純粋な動機だ。そして同時に、人を正しく理解しようという、誠実な姿勢があるように思う。彼は少し照れるように、「私は子どもの対応をするのが好きで、大人があんまり得意じゃないんです」と話す。今回のインタビューの中で印象的だった言葉のひとつだ。
その理由を聞くと次のように答えた。「私が大学の先生をやっていた頃、仕事の依頼が来たとしても、それは私が『大学の先生』だから来るんです。だけど、子どもにはそんなこと(肩書き)は関係ない。このおっちゃんが楽しいかどうか、それだけなんですよ。つまり松本敏治そのものを見てくれるんです」。肩書きや社会的立場ではなく、その人自身と向き合うこと。きっとそれは、彼自身が人と接する時に心掛けていることでもあるのだろう。
「本当に自閉症児者は方言を話さないのか」、「話さないとしたら、それはどういった理由からなのか」という疑問に、方言の社会的機能や自閉症児者の言語習得、自閉症児者のコミュニケーションの特異性など、さまざまな観点から迫っていく彼の研究。「まさか初めは本を出すまで調べるとは思わなかった」と語っているように、初めは夫婦喧嘩に決着をつけるためのエビデンス探しの研究だったはずが、謎が謎を呼んで、次なる課題へとどんどん繋がっていく。次第にそれまでの研究領域から飛び出し、未開拓のテーマに移りながら現在まで続いてきた。「人生はどう転ぶかわからないから面白い」とワクワクしているようにも見える。
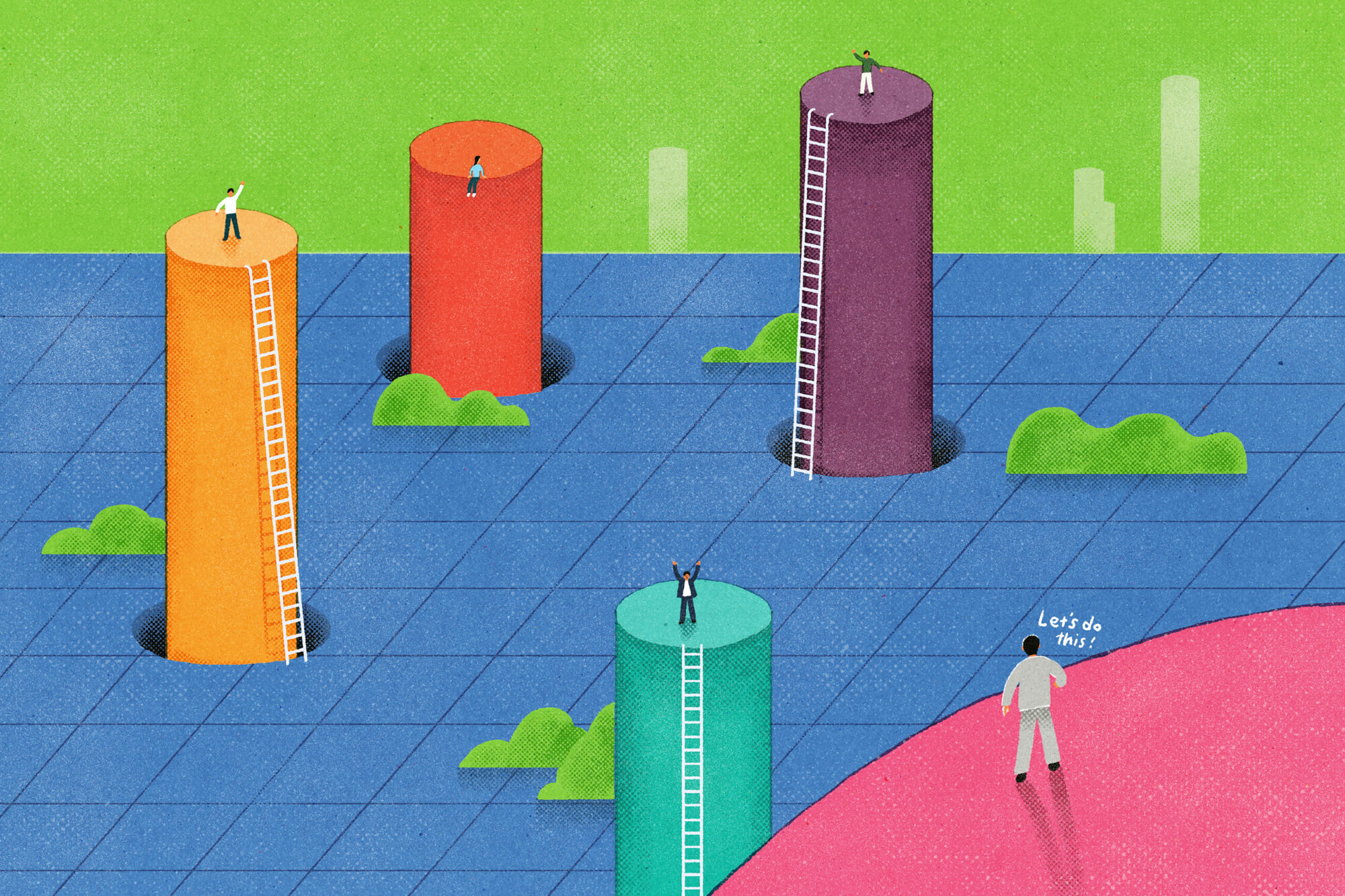
従来の「役に立つ」の外側から新たに意義を追及する
「私は妻の臨床家としての力量をかなり買っているんですよ。子どもと遊ぶ時の対応も上手いし、心理検査のレポートを見ても、こんなにわかりやすいものは見たことがないというくらい、彼女の見立てを評価している。周りの人からの信頼も得ているので、そんな人が証拠もないままにこういうことを言うのは危険かもよ?って思ったんです」
そうして彼は、自閉症と方言の関係に迫るべく「先の見えない研究」に乗り出した。最初に「何かあるかも」と思ったのは、パイロット的に行った自閉症児の方言使用調査の時だったそう。その時「研究者としての勘」が働いたということだろうか?
「いえ、私は勘は働きません。自分の頭の中に、『勘』と呼べるものがあるのかどうかもわからない。それよりも、妻が僕を評してこう言うんです。『あなたは知らないということをはっきり言うよね』って。私はあるデータが出ると、知らないことを教えてもらうためにいろんな人に喋りにいくんです。いろんな人を頼って、『このデータについてどう思う?』と。そういう僕を『腰が軽い』と言うんですよね(笑)」
そんな現場の声に積極的にリーチしていく「腰の軽さ」こそ、この研究を発展させてきた要因だろう。彼が書いた二つの著書には、各分野の専門家や現場で活動するさまざまな人が登場する。自閉症児やその家族へのアンケートやインタビューも含め、彼は抱いた疑問をどんどんシェアして、そこから生まれたコミュニケーションを楽しんでいるようにも思う。
「私は自分の頭を自分のものだと思っていないところがあって、知識はネットワークのようなものなんです。だから自分の中だけで考えるのではなく、会話をする相手がいて、その人にぶつけたものが私に返ってくる。そして相手がまた別の人にぶつけて返ってきて……というように、集団のネットワークとしてみなさんの頭も借りながら、私の知識体系の中で進めていくんです」。まるで僕らがGoogleでモノを検索するように人を頼る。だからこそ、生きた知恵が積み重なっていく。

「私は『わかり方』に凄くこだわるんです。例えば、大学教員時代は、学生に『自分のわかり方がわかったら卒業です』といつも言っていました。どんなアプローチでもいいから、『これならわかった!』と思える仕方を考えるのが大切。私は自分なりに納得するために研究をして、その成果をみんなに見てもらっているんです」
自閉症と言語習得の関係性についての研究も、いわば自分なりの「わかり方」を追求していただけなのだ。でもこの分野には先行研究もなかった。人のいない道を歩むのは簡単ではなかっただろう。実際、著書の中でも、ある研究者から「これ(この研究)が役に立つんですか?」と聞かれたことがあると告白している。これについて彼は、「私はこの研究をやっている10年間を、『暗黒の10年』って呼んでいます(笑)」と冗談っぽく言った。
「周りの人は自分の研究論文がどんなことに役立つか、どういう開発に役立つかを書けるんです。でも、私の論文はこういう話があって、調べてみたらこういうデータが出て、もしかしたら自閉症の人たちの言語習得と関わっているかもね……としか書けないんですよ」。つまりアカデミックな世界ではほとんど評価されないということ。「優れた研究業績として評価される指標の一つに『インパクトファクター』というものがあります。その論文がどれだけ引用されたかの指標で、アカデミズムとして優れたものの判断に使われたりします。だから研究としてインパクトがあるものと認められるには、フォロワーがいないと成立しません。でも、私の研究はみんなが様子見をしているのかなかなかフォロワーが出て来なかったんですよね。ようやく出てきたのが2018年頃でした」
現実に疑問をもつことが未来を切り開く
では、そうした分野に好奇心を持ち続けられたのは何故だろう。
「研究の中にもトレンドがありますが、そこには競争相手がいっぱいるし、その中には資金や人的資源に恵まれた研究機関や、大手の大学もあるわけです。だから優秀な人材もたくさん入ってくるので、その研究は私じゃなくてもいいと思います。一方で私にしか『できない』研究もほとんどないだろうけど、私しか『食いつかない』研究はあるかもな、と思うんです」

ここから伺えたのは世間体や相対的な価値ではない。自身にとってどれだけ有意義なものなのかという、絶対的な価値だ。少し大袈裟な解釈かもしれないが、彼は自分らしい生き方を実践しているんだと思う。「評価されにくく、研究意義が認知されにくい。でも、いいんです。踏み荒らされていない野原を歩いているようなもので、私が道を作っていく感覚がある。そこでは他人の理論枠に邪魔されずに、自分の理論枠で考えられる」。誰も踏んでいない土地だからこそ、そこで得られる発見は全てが新鮮なものになる。彼はまだその茨の道を歩いているのだ。
最後にこれから取り組みたい研究についても聞いてみた。ひとつは『自閉症は津軽弁を話さない リターンズ コミュニケーションを育む情報の獲得・共有のメカニズム』に出てきた、「英語しか喋らない自閉症児」のこと。「共同研究をしている国際教養大学の橋本洋輔先生が、ネットを通じて彼に日本語教育をしているんです。そうしたら少しずつ話すようになってきた。だからこれからは、なぜ日本語を話すようになったのか、そこではどういう指導をしたのか、それがテーマになってきますね」
もうひとつ彼が着目しているのはアイスランドの事例。「どうやらアイスランドでも、自閉症の子が母語よりも英語を話すという話があるようです。アイスランドは人口が36万人ほどの国で、アイスランドのテレビ局もほんの少ししかない。幼児向けの番組はアイスランド語ですが、メディアからの情報はYouTubeや近くの国にある放送局から入ってくるものが多くて、外国のアニメやドラマは英語で放送して、アイスランド語の字幕をつけるらしいんです。吹き替えをいうのはあまりない」

つまり、アイスランドという土地柄や背景が、津軽と重なる部分があると彼は見ている。「アイスランドではメディアからの情報では英語が山ほど入ってくる。でも、アイスランドの人たち同士は、アイスランド語で喋っている。メディアの英語が子どもたちの言語習得や使用に大きな影響を及ぼしているという話もあります。津軽の場合だと周囲の人が話す津軽弁(方語)とメディアの共通語ということだったけど、外国圏の中には母国語と英語の間にこれに似た関係が見られる国もありそうです」
こうして彼の関心は現在海外の事例にまで及んでおり、すでに著書の中でもドミニカの事例に触れている頁がある。最初はちょっとした興味(あるいは意地)から始まった研究が、津軽というローカルな場所を飛び出し、海を越えグローバルな研究になろうとしている。最初は理解のされなかった研究が、いつしか新聞記事やYahoo!ニュースのトップで掲載されるようになり、いつの間にか比較論が成り立つ分野になってきているのだ。またことば遣いは相手との関係性や心理的距離を形成する上で大きく影響を及ぼす。だから彼の研究の浸透やフォロワーの登場は自閉症の人たちの実態を理解し、円滑なコミュニケーションや関係づくりにおいて社会的理解を得ることにも今後直結していくだろう。
さて、文庫版ではあとがきにこんなことが書いてある。「未来を切り開く研究テーマはリアルな現実に疑問をもつことに始まるという考えもあるかもしれない」。先入観や常識に囚われずに、物事を自身の中で吟味すること。そして、身の回りにある不思議を見逃さないこと。彼の研究には人生を楽しむヒントがいくつもあると思う。


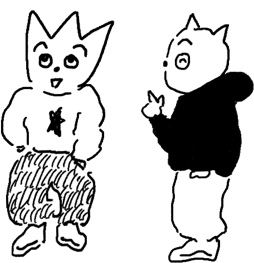


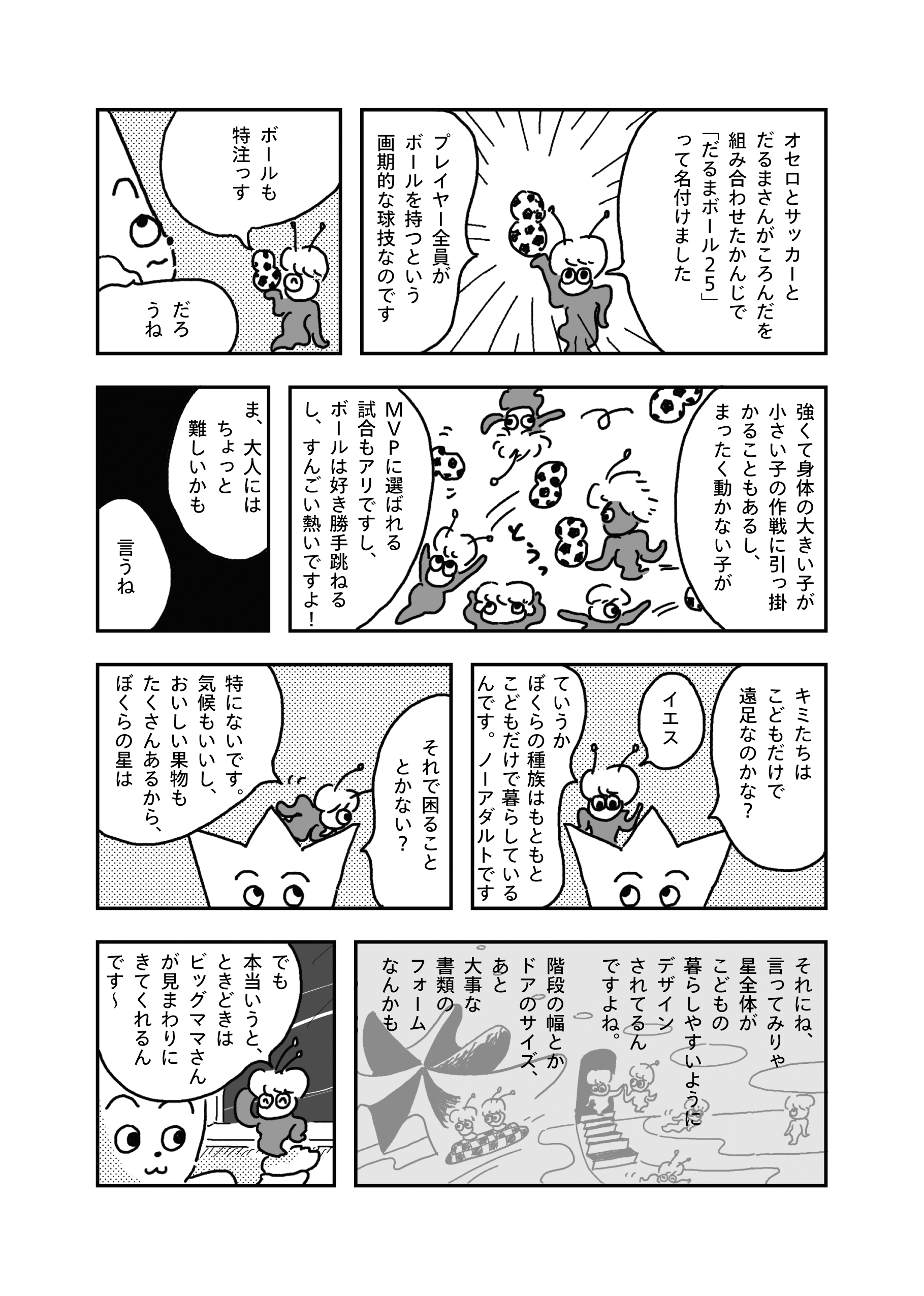


































性別、年齢、人種、職業、障害、そして”LGBTQ”さえもラベルかもしれない。それらを超えて「自分らしさ」のひとことに開放を得たとき人間関係は意外にも心地よかった。