工学院大学、東京理科大学、早稲田大学非常勤講師。法政大学、明治大学兼任講師。グッドデザイン賞審査委員。沖縄の地域住民と共に琉球石灰岩を積んで建設した「糸満漁民食堂」、斜面を活かした階段状の「はくすい保育園」、視覚障害者の支援施設「ビジョンパーク」等で国内外多数のアワードを受賞。
「ここに来ることで失われた日常を取り戻して元気になる場所」を目指し作られたビジョンパークは、視覚障がいに対する意識を変え、誰もが暮らしやすい社会にするための情報発信・集いの場として現役の眼科医が中心になって企画・設計・運営が進められた施設である。この場所を訪れる人は健常者と障がい者にただ単純に線引きできるものではない。障がいを持つ人であってもそのレベルは様々だし、精神的に落ち込んでいる人もいれば、回復に向かっている人もいる。そんないろいろな人たちがうまく融和しながら空間を共有できる場所が目指されいるのだ。

建築に人が介在すると、きっちりとした線はいらなくなる
建築というのは決める作業、要件や目指すべき物のために線を引いていく作業だという山﨑さん。彼にとってこの施設の設計は太い線を引くというよりも、線をにじませる作業だったという。
「ビジョンパークってとても危ない施設です。でも実際、施設の外に出れば段差や危ない場所だらけ。だから『なんでここでは段差があっちゃいけないんだっけ?』っていう本質的な議論から始めなきゃいけない。実際、段差があると進めないという人がいれば、近くにいる人がちょっと手を貸してあげるとか、白杖を使ってもらうとか、そういうことも考えられると思うんです。でも建築の仕事をしていると、そんなふうに誰かが手伝ってあげれば解決するという状態を想定することは望まれてこなかったんだなと思うんですよ」と山﨑さんは話す。

確かに「誰かが手伝ってくれるかも」という不確定な要素を形が決まっている建築物に取り入れるのは難しいことだ。しかし、彼はこう続ける。
「建築とオペレーションの問題を分けずに考えるといろいろな状況を受けれることができる。そこで建築は何しなきゃいけないのか、空間は何をしなきゃいけないのか、というように僕らが自由に考えるためには、人を介在させることも必要なのではないでしょうか。そうすることで、設計図にきっちりとした太い線を引かなくてもよくなるようなイメージです。一度設計した空間はなかなか変えられないけれど、そのぶん人間がその都度その都度変わればいいわけで、人間と空間がうまく使い合いできるようになればいい。でもそうすると人間に負荷がかかるわけです。それでもビジョンパークは、最初からそういうやり方を受け入れてくれました」
居てもいい場所をデザインする

ベンチと本棚を兼ねた家具、使い方を規定しないキッチンエリア、手軽にスポーツに挑戦できるボルダリングウォールなどが渦巻き状に配置されたビジョンパーク。各エリアは高低差により緩やかに区画されており、明確な利用目的よりも、癒されたい、情報を得たい、活動したいなど利用者の心のレベルに合せて居たい場所を自然に選べるようになっている。
「設計するにあたって、ここに来る人として外来の患者さんや付き添いの家族などの利用者像を提示されるのですが、それじゃ足りないわけです。例えば、死にたくなっている人と立ち直っている人。これは見た目じゃわからない。でもこの人たちが同居する状況を想像しないといけない。これが難しいことですね。僕が一番重要な最大の目的だと思ったのが、死にたくなっている人がこの場所に居られる状況を作ることだと。居てもいい理由、言い訳を作る。線を引くってわけじゃないけど、まさににじませるように、静かなところから、少しにぎやかな場所にグラデーションがかかるようなデザインになるようテクニックを駆使しています」と話す山﨑さん。

どのようなテクニックを使っているのかを問うと、「例えば、上から眺められるようにボルダリングウォールを一番下のすみっこに置いて、そこから少しづつ上がっていくような小さな地形を作っているんです。元気なもの同士ならいいんだけど、そうでない人がいる場合、目線がそろうのって結構きつい。目線が合う状態を作ると所在が生まれないから、元気のない人のために視線を外してあげないと。目線をずらすだけでも同じ空間を共有しやすくなるでしょ」
「あるいは背中が守られているような少し囲われている場所を作る。あと、『居合わせる』と呼んでいるのだけど、反対方向を向いて隣り合う座り方で自然と会話が始まるような場所も作りました。元気がある人だって、今日は絶対話しかけられたくないという時は、話しかけられないような場所を選びます。反対に、積極的に話さなくてもいいけれど心は少し開いた状態だという人は、少しオープンなスペースに座るんですよ。その人がそこを選んでいるというのが重要だと思うんです」
利用者像を眼科に来る人、外来の人、付き添いの家族というような役割で定義するのではなく、見た目では区別できない心の状態にも寄り添う。ビジョンパークには、そうやって緩やかな線が引かれていたのだ。

一人で公共の場に居ることができる豊かさ
山﨑さんがビジョンパークの設計を手掛けた時に、「居方(いかた)」の研究をしている近畿大学の鈴木毅教授の話を参考にしたという。その中で印象に残っている話があるそうだ。それは、今までの建築家がしてきたた仕事は「見る/見られる」を意識して設計してきたということ。「それってすごく乱暴なことなのではないかと。そこでは人間の存在がのっぺらぼうになっているんです。もし元気がなかったら、『見る/見られる』なんて耐えられない状態だと思う。先生はそこに『居方』という概念を入れて、『居る』という状態と『見守る』という関係に置き換えて話していました。例えば、元気のない人を見守るという関係性というのは、双方向じゃないんですよ。一方向だけなので居方という考え方の中ではすごくフィットする」

そんな状態を見事に表した絵があるという。19世紀末のフランスの新印象派の画家ジョルジュ・スラーによる代表作『グランド・ジャット島の日曜日の午後』だ。点描法を用いてセーヌ川の中州で人々が思い思いに過ごす夏のひとときを描いている。この作品が、ビジョンパークの設計の大きな手掛かりになったという。

「これ、重要なのはみんな同じ方向に川に向かってそれぞれがいることなんです。公共っていうとみんなで一緒に同じ場所にいるということを思い浮かべますよね。でも実は、一人で公共を感じられる状態というのもすごく豊かだと思うんです。仮説ですけど、それはまわりに人がいる中で一人でいる状態ということ。この絵はそういうことをいっているんだと思ったんです。例えば銭湯に行ってぼんやりするとか、カフェに行ってまわりにお客さんがいる状態とか。そうすることで、今まで無関係だったまわりにいる人たちをなんとなく認識するような想像力が生まれているんではないかと。遠くにいる人たちを見ることで、ある種の関係性があると思えるような気分で眺められる。これは居方の考え方にも通じるのですが、居方って形容詞を当てることなんですって。今まで居場所というのは『働く』とか、『眠る』とか動詞的だったんです。さっきの絵のような居方は形容詞的に言うと『思い思いに』ということになるのかな」
わからないことを共有することで生まれた感動
「僕は死にたくなったこともないし。目が見えなくなったこともない。その人のことがわかるって言えないんですね。当然安易にわかっちゃいけないし。わからないから、簡単に言えないですよ」と赤裸々に想いを吐露する山﨑氏だが、ビジョンパークの設計をしていく中で、心の突っかかりのようなものをパッと超える瞬間があったという。
「これ設計をした時、あまりにも危ないだろうと、モックアップを作って事前の検証をしたいと言ったんです。そうしたらここ(神戸アイセンター)の先生である三宅さんが利用者さん連れてきてくれて。それまで変な先入観がいっぱいあったんですが、モックアップを目の前にした利用者さんは『これくらい全然平気だ』って答えるんです。『でも世の中には全然平気じゃない状態っていっぱいあるんじゃないですか?』って僕が聞くと、『いや俺には大丈夫だ』って。僕ら、設計するときは慎重になったほうがいいと思っていつも『本当に大丈夫か?』と心配になりながらアイデアをいくつも重ねてしまうんです。でも利用者さんたちにしてみたら『もう平気だ』と。だからといって、すべての人にとって平気な施設だということではなくて、ダメな人もいっぱいいると思うんです。でも利用者さんたちの生き方にすごく感動しちゃって」

「他にも、この場所に置かれている本は、ブックディレクターの幅さんが選んでいるんですが、視覚障がいの施設なのに点字ではない本が置かれているんです。擦るとにおいが出る本とか、立体になる本とかね。その中にあった『どっとこ どうぶつえん』って本のことをよく覚えています。お母さんと子どもと視覚障がい者の人がいる中で『これ何に見えますか?』と聞いてみると、お母さんだけがわからない。視覚障がい者の人は薄眼で見てるからぼやっとシルエットが見えるし、子どもは感覚でわかる。なんかね、人間って強いとか弱いとかがあるんだけれど反転するところもあって。それに素直に感動してしまいました」

にじみが生み出す新しいカタチ
例えば、一本の線が分断をイメージさせるように、形というものは人の行動にも作用を与えることがある。山﨑さん曰く、マンションの廊下で堂々と会話をする人はいない。廊下のわきには扉があって、それが開くと住人の部屋の中が見えてしまう。マンションの廊下は、そうやって不用意にプライバシーに立ち入ってしまう危険性がある場所だと私たちにインプットされているのだ。つまり、環境が人の行動を規定しているということ。そのように環境に規定された今の私たちの生活の中には、「なんにでも触れ合っていい」というような場所があまりないと言う。
「例えば人間の関係というのはすごく限定されていて。僕、息子がいるんですが、朝起きて、お父さんとお母さんに『おはよう』と挨拶して、学校に行ったら先生がいて、友達がいて、家帰ったら友達と遊びに行って、寝るんだと。この状況を食べ物だと考えるとバランスが悪いですよね。お父さん、お母さん、先生、友達とすごく偏っている。それは要するに他の人と触れ合える場所がないから。だからうちの息子が事務所に来て他のメンバーたちと、この空間に一緒にいるとか、近所の酒場で一緒にご飯を食べるとか。いろんな人に触れ合わさせたほうがいいと思っています」

「だから、僕は建築は環境だと思うんだけど、環境が失われていくと人間との関わりをみんな忘れちゃうんだろうなって思うんです。僕は建築が家族の形をはっきりさせているんじゃないかなと思っていて。マンションに住んでいると防火や防犯の観点からしっかり区画されていて、この区画に住んでることが『家族』っていうふうになる。でも、もし建築が変わったら、マンション自体が区画になって大きな家族だって錯覚するようなことも起こるんじゃないかと思って。そして一回そういう体験をすると、その人はだんだんそういうふうにふるまえるようになっていく。だから建築はもっと太い線をにじませていったらいいのにと思っているんです」


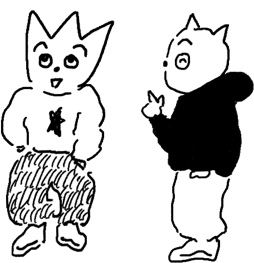




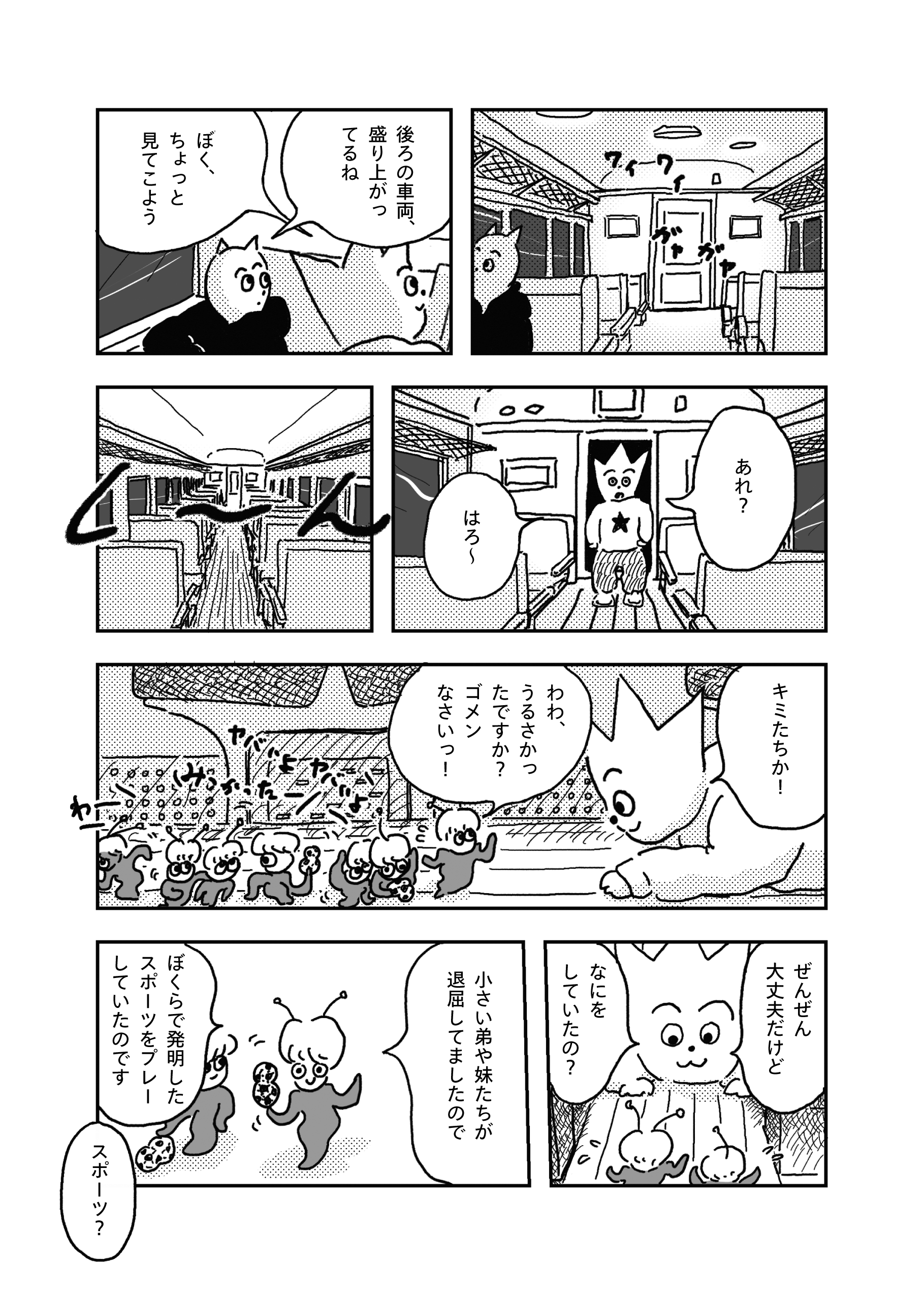


































何年か前に菅原さんとお話ししたが、その時に見せてもらった”岡じい”の役者魂と表情が忘れられません。見ているこちらも満たされた気持ちになってくるから不思議。