1983年栃木県宇都宮生まれ。劇作家、演出家、俳優、介護福祉士。「老いと演劇」OiBokkeShi主宰。青年団に俳優として所属。2010年より特別養護老人ホームの介護職員として勤務。2012年、東日本大震災を機に岡山県に移住。認知症ケアに演劇的手法を活用した「老いと演劇のワークショップ」を全国各地で展開。
介護と演劇は相性がすごく良い
OiBokkeShi―オイボッケシ。愛らしい郷土玩具をイメージさせる名前は、「老い・ボケ・死」をもじったものだ。長らく東京で俳優として活動してきた菅原さんが介護の世界に飛び込んだのは、20代後半のこと。別のスキルを身につけようと働き始めた老人ホームで、多くの高齢者と接するうちに、介護や認知症の概念がどんどん覆されていったと話す。
「お年寄りほど良い俳優はいないのでは……と劇的な感動を覚えました。腰の曲がったおばあさんがゆっくり歩いているだけなのに、そこには個性や人生が滲み出ている。聞けば、青春時代を満州で過ごしたりシベリア抑留の経験がある方もいて、老人ホームには様々な人生が詰まっていることを知りました」

とはいえ、認知症の方とのコミュニケーションは一筋縄ではいかないことも多い。代表的な障害としては、物忘れが激しくなる記憶障害や現実と認識にズレが生じる見当識障害等が挙げられる。例えば、老人ホームをビジネスホテルと思い込み、介護職員を時計屋さんと勘違いする、なども日常茶飯事だ。
「常識的にはおかしな言動や失敗が増えていきますが、認知症の方にとっては仕方のないこと。にもかかわらず、いちいち正したり失敗を指摘したら彼らの気持ちが傷つくのでは?と思うようになりました。喜怒哀楽などの感情はしっかり残っているためです。大切なのは、理論理屈にこだわらず感情に寄り添う関わり方。そこでは、時には介護者が『演じる』ことも重要なのでは?と思うようになったんです」
時には受け入れたり、(実際は無いものを)見たふりをしながら、認知症の方が見ている世界を尊重しつつ現実との折り合いをつけていく。そんな関わり方を、菅原さんは学んでいった。事実、彼らの感情を無視してこちらの現実に引きずりこむような対応では認知症の症状が悪化することも多く、コミュニケーションの重要性が伺える。
高いやりがいの反面、ときにきつい仕事とも言われる介護職だが、人間味溢れるこの現場で菅原さんが感じたのは、どこまでも豊かな老い・ボケ・死の世界。それらを、演劇を介して伝えたい!という想いを強めていった。
看板俳優は94歳。できることが増えている
OiBokkeShiの看板俳優は「岡じい」の愛称で親しまれる岡田さん(94歳)。彼無くして今の劇団は存在しないと、菅原さんは彼との出会いを振り返る。2012年、岡山に移住した菅原さんは劇団を立ち上げるべく、メンバー募集も兼ねて演劇と介護のワークショップを開催。その開始1時間半前に、一番乗りで訪れたのが当時88歳の岡田さんだった。

「芝居に対する気合が感じられましたし、耳が遠いのに芝居の時だけ良くなったりして、この人は何かすごいぞと。聞けば、昔から芸事が好きで、映画俳優を目指し数々のオーディションを受けてきて、今村昌平監督の映画にもエキストラ出演した経験がある、と。実は、演劇経験の豊富な方だったんです。また、認知症の奥さんの介護もしてもいた。まさに老いと演劇を体現している人だと思いましたね」
そんな岡田さんとの芝居作りは試行錯誤の連続。演出家として完成度を求めるあまり岡田さんにダメ出しをしてしまった時期もあった、と菅原さんは省みる。以来、岡田さんそのものの魅力をうまく引き出すことで、なるべく負荷をかけないよう工夫を重ねている。岡田さんの境遇と近い役を用意したり、岡田さんが普段よくする話を台本に組み込んだり、といったことだ。
「例えば『ポータブルトイレットシアター』。岡田さんが台本通りにいかない時、共演者は戸惑い軌道修正を図りますが、その困っている空気ごとお客さんに楽しんでもらう。共演者は、俳優という名の介護者になっているんです。以来、この『失敗もOK』な方法論でやっています」
また、基本的に台本は読みこまない岡田さんだが、ピンとくる印象的なセリフは一回読んだらすぐに覚えてしまうのだという。逆に言えば、良いセリフを書かなければならない。そこで僕は試されているんですよ、と菅原さんは苦笑する。

岡田さんの出演シーンは、本人の希望で年々長くしてきた。「認知の巨匠」(2019年)では2時間出ずっぱり、「ポータブルトイレットシアター」では1時間半出ずっぱり・喋りっぱなし。94歳になり日常ではできないことが増える一方、舞台上では「できることがどんどん増えている」と菅原さんは不思議がる。
「岡田さんは単なるおじいさんではなく、僕にとっては大事な演劇仲間。信頼関係ができてくれば、お互いが引き出しを開け始め、その中ではできることが増えていく。それを岡田さんは身をもって教えてくれます」
誰もが異質な世界を生きている
OiBokkeShiの舞台では、高齢者で介護者でもある岡田さんのような役者もいれば、認知症の人が出ることもある。初めて観るなら、戸惑う人もいるかもしれない。表現の上で菅原さんが大事にしていることは何か。
「認知症か否かではなく、誰もが違う世界を見ている一人の人間なんです。それを踏まえて、認知症の人が異質な世界を見ているのではなく、実は自分も異質な世界を見ているのでは?と気づかされるような体験をしてもらいたくて、芝居を作っています」

演劇と介護、どちらの現場で関わる人も、菅原さんにとっては「認知症の人」ではい。それぞれ強烈な「○○さん」なのだと声を強める。そんな彼の視点は、認知症に留まらず、価値観の違う人を理解する上での大きな指針になりそうだ。
「人は、自分が見ている世界に支配されてしまいがちです。それを忘れずに、コミュニケーションに意識的になることが大切です。あまりにも異なる世界を見ている人に関しては、寄り添うことで心が通じ合う瞬間が生まれて、そこから対話の可能性が見えることも多いです」
実際、奥さんを介護中の岡田さんも、演劇を介して奥さんへの接し方が変わったのだとか。これを菅原さんは「ボケを演劇で受け入れる」と表現する。
「奥さんの物語の脇役になってあげることで、穏やかな気持ちで介護に向かうことができているようです。『演技』というと悪いイメージもありますが、自分の都合を押し付けず相手の世界に寄り添うために生まれる演技なら、これほど素晴らしいものはないと思います」
演劇には人を生かす力もある
介護が菅原さんのターニングポイントになったように、OiBokkeShiとの出会いは岡田さんの人生を大きく変えている。
「岡田さんにとって演劇は命そのもの。できることが増えたり、奥さんの介護のストレスも減ったり、心身の健康に繋がっているのは明らかです。演劇には人を生かす力もあるのだと、彼が身を以て教えてくれています」
そんな岡田さんを通して、菅原さん含む共演者は演劇の力を感じ、観客の皆さんも元気になる。菅原さんが毎回の舞台で目の当たりにしているのは、そんな良い循環だと言う。
今、日本は超高齢化社会の最中。「老い・ボケ・死」の固定概念を崩すOiBokkeShiが世代を越え広まっているのは、至極自然な流れに思える。コロナ禍で数週間先の公演予定さえ定まらない日々が続くが、今後はどんな展開を予定しているのだろう。

「コロナ禍であっても介護は決してストップしません。岡田さんとの関わりにおいては、演劇も同様で、認知症の悪化や身体能力の低下を防ぐためにもOiBokkeShiとして働きかけ続ける必要があると感じます。この演劇の力を信じて、今後は地域の高齢者や演劇初心者の人にも、もっと芝居に参加してもらえるようにしたいです」
オンライン稽古にも挑戦し、今後は介護と演劇に関するプラットフォームを作る予定もあるという菅原さん。介護と演劇、双方の現場での気づきを落とし込んだ表現は、今の日本を映す鏡となり、ますます多くの人の心に響きそうだ。


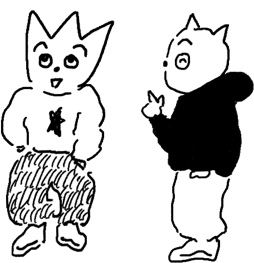

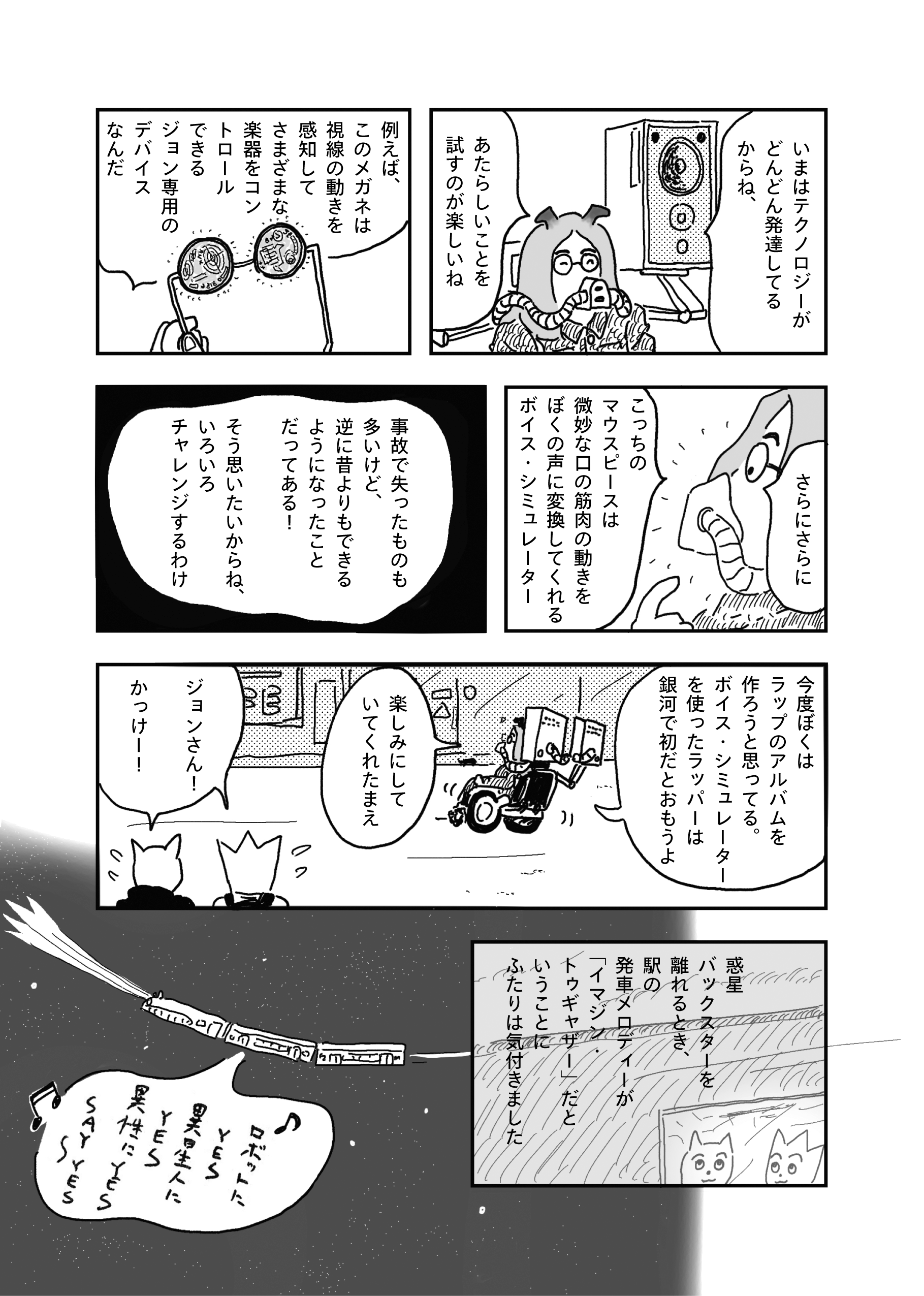


































自分の身体に正直な方法を探ってきた森田さんのパフォーマンスは、多くの人々に表現の扉を開かせ、自分自身と向き合う場を生み出すのだろう。表現の可能性にドキドキした。