1984年生まれ。社会人経験を経て、保育士となり、子育てコミュニティ「asobi基地」、「こどもみらい探求社」を設立。プライベートは、神戸市長田区でこどもと犬との暮らしを楽しんでいる。共著に『いい親よりも大切なこと 〜子どものために “しなくていいこと” こんなにあった!』(新潮社)。
「福祉」に対するイメージへの違和感に、こどもたちが答えをくれた

おやこ保育園は全国の親子のための場だ。けれど、参加者がこどもの遊びや、こどもとの関わり方を体得するにとどまらないと小笠原さんは言う。そのビジョンを知るためにも、まずは彼女が長年対峙してきた「福祉」についての話から始めたい。
小笠原さんの「福祉」にまつわる原体験は、小学生の頃の親友が生まれつきハンデをもっていたこと。その後、福祉を学ぶことで「差別のない社会」「豊かな社会」を目指せるのではないかと思ったことから、四年制大学の福祉学部へ進学。学問として学ぶだけでなく、障害をもつ児童や高齢者の現場に頻繁に足を運んだ。
「福祉という言葉を使うと、たちまち社会から分断されるように感じたんです。たとえそれが、豊かな社会を目指す目的であっても。周りに障害者、高齢者、こどもがいなければ他人事に感じられてしまう。関わっていると言うと、なぜか『えらいね』と言われる。福祉という言葉がもつイメージに対して、ずっとモヤモヤしていました」
その答えをくれたのは、大学卒業後に勤めた保育園で出会った1歳児クラスのこどもたちと、そのクラスを一緒に受け持った先輩保育士だった。

「1年間こどもたちと過ごしてわかったのは、どの子も他人を否定していないということでした。1歳というとまだほとんど言葉も話せない年齢ですが、誰もが『その子はその子』とお互いを知り合い、認め合っている。そうして自然と世界が成り立っているを目の当たりにしたんです。同時に、一緒に働いていた先輩の姿から、そのために必要な条件があることにも気づきました。それは、『大人が自分の主観だけでジャッジしないこと』。このことを大人に伝え、大人がそうやってこどもたちの隣にいることができたら、差別や固定観念のない社会になるのでは?と気づいたんです」
小笠原さんがこどもたちの社会に見たのは、違いを認めてその人らしく生きる=福祉社会の縮図とも言えるもの。それの「違い」を、「凸凹」という言葉で彼女は表現する。
「福祉の考えだと、ハンデがあってもそれを個性として捉え、できることを見つけ、その人がその人らしく生きていけるサポートをしていきます。対して、保育や教育の世界では、違いをならして平らにする傾向がまだまだ根強いと感じていて。完璧にしていくのではなく、その子らしい個性=凸凹のままで育つことのできる環境をつくるという福祉的な考え方を、そのまま保育や教育にも当てはめていく方法はないのだろうかと思ったんです」

そうして決意を新たにし、保育園を飛び出した小笠原さんは、小竹さんと共に会社を立ち上げ、おやこ保育園開設に向けて進んでいく。個々がのびのびその人らしく、という考えを体得した親子が増えれば、その考えが親子から家族に、家族から地域に滲み出していき、結果として分断のない社会に近づくことができるかもしれない。だからおやこ保育園は、そんな社会につながる循環を作る装置なのだと小笠原さんは言う。コロナ禍でオンライン化&無償化(寄付で運用)を決意したのも、その根底の想いに立ち返ったからだと小笠原さんは前を向く。
「私たちの活動は、実はこどもに何かしたいわけではなくて。こどもたちはすでに自分らしくのびのび生きているので、そのまんま大きくなってねと言える環境をつくっているんです」

親も子も。おやこ保育園はどちらも主役

おやこ保育園は基本的に親子で参加し、10回の通園を経て卒園する仕組みだ。独自のメソッドは自治体や保育施設からの引き合いも多く、これをまとめた書籍も人気だ。世の中には親子向けの教室は多数あるが、おやこ保育園の特徴はどこにあるのだろう。それは、「主軸として “こどもが主役の時間”と“大人が主役の時間”を同じボリュームで設けていること」だと小笠原さんは話す。
“こどもが主役の時間” では、毎回異なるテーマを設け、身近にあるもので遊ぶ。その際に伝えていることは「とにかくまずは手を出さないで“観察”してみてほしい!」ということ。家庭にある物を積極的に使うのも、新品のおもちゃでなくても、いかにこどもが自由な発想で楽しめるかを実感してほしいから。
「こどもは初めて見る物に出会うとき、固定観念がないので自由な発想で見て、発見し、関わろうとします。『これはこう使うんだよ』と教えることで正しい使い方などを学べることもありますが、自ら発見する機会を奪うことにもなってしまうんです。」
我が子が自ら遊びを見つける瞬間を目の当たりにした親は、こどもは “そこにあるもの” の中に楽しみを見つけ、世界を広げていけるということに気づいていく。
「そうすることで親が何かしなくちゃ!と焦らなくなり、心に余裕がもてるようになる。ただこどもの隣に “いる” ことができるようになっていくんです。我が子を信じて見守れる大人の隣で、こどもは自ら成長していくんですよね。」

対して、後半の “大人が主役の時間” は、大人が子育てをしていく上で抱えがちな “〜しなければならない” という概念を取っ払い、選択肢を広げていくことを目的としている。
「『コミュニケーション』や『イライラ』など毎回異なるテーマに沿って同期メンバーたちと語り合います。話していく中で、自分とパートナーはこんなにも得意なコミュニケーション方法が違うんだ!とか、イライラしちゃうのは私だけじゃないんだ!など、自ら何かに気づいていく。“自ら”というのがポイントで。子育てや家事、仕事をしていると立ち止まって考える時間ってなかなか作れないですが、この時間の中で思考や感じていることを言語化することで自分の“今の状態”が見えてくる。気づけたら、次のアクションを考える。そうやって自分の中を掘っていくことを大切にしています」
クラス終了後には宿題があり、クラスで気づいたことや学んだことをSNSを活用しながら暮らしの中で実践していく。そして「考える→気づく→実践する→振り返る」というサイクルを日常の中で繰り返していくのだ。
そんなプログラムの根底には、主宰の2人が保育の現場で感じていた違和感がある。
「『ママだから/ パパだから、うまくできるよね!』という親への無言の “プレッシャー” が当たり前のようにあるなと思いました。いい親になろうと頑張ることが、結果として親の自分らしさを薄れさせていくことにつながってしまう。理想の親を自分自身が求めていくということは、すなわちこどもにも理想のこどもを求めてしまうことになる。それも無意識に。それなのに保育の現場では『こどもは自由にのびのびと!』という言葉だけが飛び交う。こどもだけではなく、こどもに影響を与える大人こそが “その人らしく・のびのび” 生きることが必要だと感じています」
核家族だけど一人ぼっちじゃない。拡大家族的な暮らし

小笠原さんが2017年に生活拠点を移したのは、下町情緒がそこここに残る神戸市長田区。この地域に多い、昭和の風情香る長屋に生活と仕事の拠点を構え、活動している。近隣には年季の入った市場や昔ながらの商店街、また多国籍な飲食店も多い。あたりを少し歩くだけで、ファミリー層にお年寄り、また韓国やベトナム籍のファミリーなど、幅広い世代・国籍の人が暮らしているのが手に取るようにわかる。関東暮らしが長く縁もゆかりもなかった小笠原さんだが、初めてこの町を訪れた時に「ここに住みたい!ここで子育てしたい!」と直感で決めたと話す。
「少し私と一緒に歩いてもらえれば分かるように、町の至る所で声をかけてもらえます。ご近所付き合いが濃厚で、助け合いの文化が根付いているんです。ご近所さん同士で一匹の猫を飼っていたり、こどもの託児やお迎えをお願いし合うのも日常茶飯事です。近くには誰でも出入り自由なオープンな介護施設などもあり、そこでは色々な世代・国籍の人が高齢者と交流しています」

地震があれば「大丈夫!?」と、ご近所さんが玄関まで見に来てくれることもあると言う。聞けば、この辺りは阪神大震災の影響が大きかった地域というから、人々の絆は長年育まれてきたものとも言える。小笠原さん一家は核家族で、育児がワンオペになることも多々。しかしここには支えてくれる人がたくさんいる。この町にあるのは、そんな “拡大家族的” な暮らしだ。
「ほとんど知り合いのいない状態で移住してきましたが、子育てに不安を感じることはありません。それはなぜかと考えてみると、息子だけでなく私のことも気にかけてもらえているから。しんどい時に弱音を吐ける人がいるし、きっと助けてくれる人が家族以外にたくさんいる。街全体が私にとって安心・安全な環境で、家のような場所なんです。さらにその中に、いろんなの個性・価値観の人がいる。とても豊かな暮らしだなと常々感じています」

そんな彼女の姿は、多様性のある街に自らを置いてみることで、豊かな社会を探る実験を楽しんでいるようにも見える。その根底にはやはり、固定された様々な “線” を溶かしたい、という想いが注がれてい る。
「実は私はもともと心配性で、食わず嫌いなところがあったんです。でも苦手に感じていたことも、やってみると意外と大丈夫だったり、自分の心地の良い加減がわかったりして、行動に移すことで見える世界がいかに変わるかに気づきました。だから今は一歩踏み出せずに悩んでいる人に、自信をもってアドバイスしています。自分に合うかわからないことも、とにかくやってみたり、他人と価値観をシェアしてみたりすることが、様々な “線” を溶かすきっかけになるはず。そのためにも、大人ももっとトライアンドエラーのできる社会になると良いなと思います」



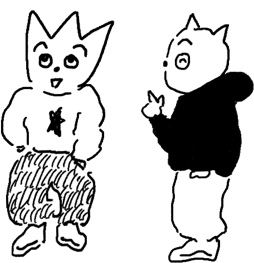



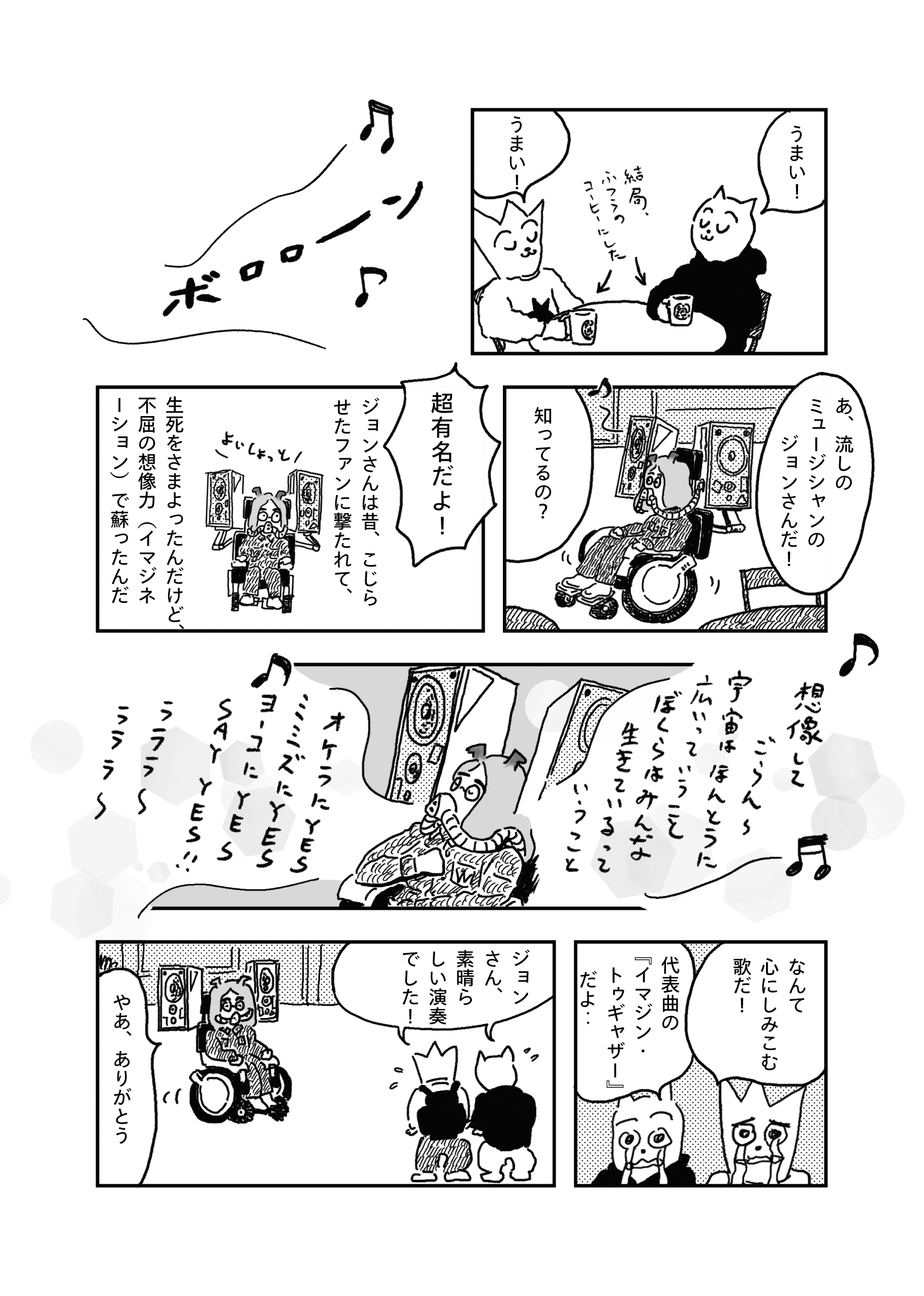


































共感と気づきが多く、課題の本質をどう捉えていくかのプロセスが見える記事でした。自分の心がどこで動くのか、感じながら読んでみてください!